世界的な人気を誇る「ウィッチャー」シリーズの原作者アンドレイ・サプコフスキ氏が、
『自身の小説に「ウィッチャーの流派」という概念を登場させたことを後悔している』
と発言し、大きな波紋を広げています。ゲーム版で根幹をなす設定にまで成長したこの要素を、作者は「まったく不必要だった」と語り、その意図せぬ発展に複雑な心境を覗かせました。
発端はたった一文の「狼流派」
この発言は、ウィーンで開催されたコミコンでのQ&Aセッションで飛び出したものです。
サプコフスキ氏は、自身の短編集『最後の願い』に「狼流派」という言葉が一度だけ登場することに触れ、それが意図しない形で後世に大きな影響を与えてしまったと語りました。

“狼流派”に言及した一文が、なぜか『最後の願い』に入り込んでしまいました。あとになって、発展させる価値はなく、物語的にも不適当で、プロットに弊害をもたらすことさえあると思うようになりました。
そのため、その後は二度とウィッチャー版グリフィンドールやスリザリンに言及することはありませんでした。決してね。
サプコフスキ氏にとって、それは物語の本筋には関係のない、取るに足らない一文だったようです。
ゲームで花開いた「流派」の世界観
しかし、この「流派」という設定に光を当てたのが、CD PROJEKT REDが開発した大人気ゲームシリーズでした。
ゲーム開発陣はこの設定に強く惹かれ、ゲラルトが所属する「狼流派」以外にも、独自の解釈で世界観を大きく拡張しました。
ゲームシリーズや関連作品には、現在少なくとも以下の流派が登場します。
- 狼流派 (School of the Wolf)
- 猫流派 (School of the Cat)
- グリフィン流派 (School of the Griffin)
- 熊流派 (School of the Bear)
- 蛇流派 (School of the Viper)
- マンティコア流派 (School of the Manticore)
- 鶴流派 (School of the Crane)

さらに、次回作『ウィッチャー4』を示唆するティーザー画像では「オオヤマネコ流派 (School of the Lynx)」のメダルが描かれ、ファンを熱狂させたのは記憶に新しいところです。
原作者の葛藤と、戸惑うファンの声
原作者の「まったく不必要でした」という発言は、多くのゲームファンに驚きと、ある種の戸惑いを与えています。SNSや海外のフォーラムでは、様々な意見が飛び交いました。
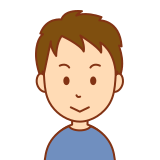
ゲームからウィッチャーを知った自分にとっては、流派は世界観の根幹だ。各流派の伝説や装備を集めるのが最高に楽しかったのに
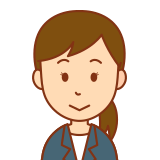
サプコフスキ氏の気持ちもわかる。でも、CDPRが流派を掘り下げたからこそ、ウィッチャーの世界はここまでリッチになったんだと思う
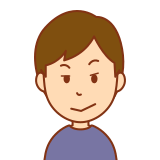
まるで自分の子供が、知らない間にタトゥーを入れて帰ってきたのを見る親の気分なのかもしれないね
ゲームでの体験を重視するファンからは、流派の設定を擁護し、その魅力を語る声が多く見られます。

一方で、「作者の言う通り、原作のゲラルトはもっと孤高の存在だった。組織に分類されるのは少し違う気がする」と、サプコフスキ氏の創作理念に共感する原作ファンからの意見も聞かれます。
作者の意図を超えた”嬉しい悲鳴” — 今後の選択肢は?
この状況は、原作者の意図を超えて作品世界が成長し、巨大なフランチャイズになったことの証左と言えるでしょう。まさに嬉しい悲鳴とも言えるこの矛盾に、サプコフスキ氏自身も今後の対応を決めかねているようです。
彼が提示した選択肢は、大きく分けて二つ。
削除するという選択

「『最後の願い』の今後の版から“流派”に関する一文を削除するのがいいかもしれません」と語るように、自身の正史(カノン)からこの概念を完全に消し去るという道です。
これは作者の当初のビジョンを維持する最もシンプルな方法です。
自らの手で再構築する道

もう一つは、「その後の作品で何らかの形で発展させて明確にしたくなる可能性もあります」と示唆したように、原作者自らの手で「流派」の設定を再定義し、自身の物語に組み込むという道です。
ウィッチャーのメダルの意味や、流派の成り立ちを作者自身が語るとなれば、多くのファンが歓喜することは間違いありません。

原作者の小さな後悔から生まれた設定が、今やシリーズの欠かせない魅力の一つとなっているこのねじれ。サプコフスキ氏が今後どちらの道を選ぶのか、そしてゲームシリーズがそれをどう受け止めていくのか。ウィッチャーの世界は、まだまだ私たちをワクワクさせてくれそうです。



コメント